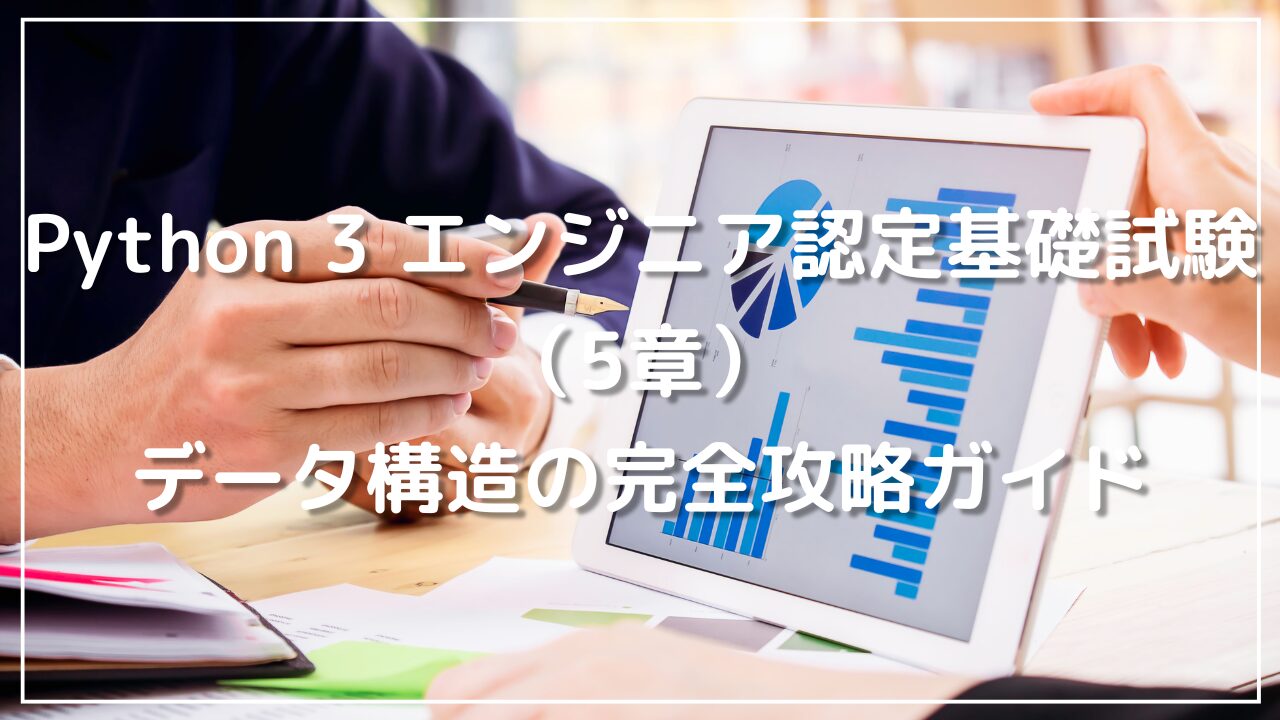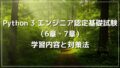Python 3 エンジニア認定基礎試験 (5章)は、データ構造に関する深い理解を問われる重要な章です。この試験を受ける方は、リスト型や辞書型といった基本的なデータ構造の操作だけでなく、リストをスタックやキューとして利用する方法、リストの内包表記やネストしたリストの扱い方など、効率的なデータ処理を学ぶ必要があります。
さらに、タプルや集合型といったデータ型の特性を理解し、それらを適切に活用するスキルも求められます。また、del 文を使用したデータの削除や、ループのテクニック、複雑な条件分岐の処理、シーケンス型とその他の型の違いを把握することもポイントとなります。
この記事では、試験の範囲である「リスト型についてもう少し」から「シーケンスとその他の型の比較」までの重要トピックを詳しく解説します。これにより、効率よく学習を進めることができ、Python 3 エンジニア認定基礎試験 (5章)に向けた準備が万全となるでしょう。
他にもBe Free Techではエンジニアの人が知らないと損する情報を紹介してますのでご覧ください!
- リスト型の活用方法やスタック、キューとしての利用方法を理解できる
- タプルや集合型、辞書型といったデータ構造の特徴を把握できる
- 条件分岐やループのテクニックを活用した効率的なプログラム構築を学べる
- シーケンス型とその他のデータ型の違いや適切な使い分けを理解できる
Python 3 エンジニア認定基礎試験 5章 データ構造 前半

- リスト型についてもう少し
- リストをスタックとして使う
- リストをキューとして使う
- リストの内包表記
- ネストしたリストの内包表記
- del 文
リスト型についてもう少し
Pythonのリスト型は、多様な用途に応じて柔軟に使える強力なデータ型です。リストは、複数の要素を順序付きで格納でき、数値や文字列、さらには他のリストも格納することができます。また、リストは可変型であり、要素の追加や削除が自由に行えます。これにより、データの操作や管理を効率化することが可能です。
さらに、リストの便利な特性としてリスト内包表記があります。リスト内包表記を使用すると、簡潔なコードで新しいリストを生成できます。また、リストメソッドを活用することで、検索、並べ替え、フィルタリングなどの操作をシンプルに行うことができます。
リスト内包表記の活用
# 1から10までの数値の2乗を含むリストを生成
squares = [x**2 for x in range(1, 11)]
print(squares)
# 出力: [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]
リストメソッドの利用
# リストの操作
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits.append("orange") # 要素を追加
print(fruits) # ['apple', 'banana', 'cherry', 'orange']
fruits.remove("banana") # 要素を削除
print(fruits) # ['apple', 'cherry', 'orange']
リストをスタックとして使う
Pythonのリストは、スタック(後入れ先出しのデータ構造)として使用することができます。スタックでは、新しい要素を追加する際に append() メソッドを使用し、要素を取り出す際に pop() メソッドを使用します。このシンプルな方法により、データの順序を管理する必要がある場面で効率的に活用できます。
スタックは、再帰的な処理やブラウザの履歴管理など、順序が重要なタスクでよく利用されます。ただし、大量のデータを扱う場合は、リストの計算量が問題となる場合があるため注意が必要です。
スタックの基本操作
stack = []
# 要素を追加
stack.append(1)
stack.append(2)
stack.append(3)
print(stack) # [1, 2, 3]
# 要素を取り出す
print(stack.pop()) # 3
print(stack.pop()) # 2
print(stack) # [1]
スタックの活用例(括弧のバランス確認)
def is_balanced(expression):
stack = []
for char in expression:
if char == "(":
stack.append(char)
elif char == ")":
if not stack:
return False
stack.pop()
return not stack
print(is_balanced("((()))")) # True
print(is_balanced("(()")) # False
リストをキューとして使う
リストはキュー(先入れ先出しのデータ構造)としても利用できます。キューでは、新しい要素を追加する際に append() メソッドを使用し、要素を取り出す際に pop(0) を使用します。ただし、この操作はリストの先頭を処理するため、計算量が増加する可能性があります。大量のデータを効率的に扱う場合は、標準ライブラリの collections.deque を使用するのがおすすめです。
キューは、タスクのスケジューリングやバッファリングのように、データが順番に処理されるシナリオで役立ちます。
キューの基本操作
queue = []
# 要素を追加
queue.append("A")
queue.append("B")
queue.append("C")
print(queue) # ['A', 'B', 'C']
# 要素を取り出す
print(queue.pop(0)) # A
print(queue.pop(0)) # B
print(queue) # ['C']
キューの活用例(簡易的なタスク管理)
tasks = []
# タスクを追加
tasks.append("Task 1")
tasks.append("Task 2")
tasks.append("Task 3")
# タスクを順番に処理
while tasks:
task = tasks.pop(0)
print(f"処理中: {task}")
# 出力:
# 処理中: Task 1
# 処理中: Task 2
# 処理中: Task 3リストの内包表記
リストの内包表記は、リストを効率的に生成するためのPython独自の記述法です。この機能を使うことで、従来のfor文を使ったリスト生成に比べて、より短く簡潔なコードを書くことができます。リストの内包表記は、リストの要素を生成する式をfor文や条件式と組み合わせて記述します。
例えば、既存のリストを加工して新しいリストを作成する場合や、特定の条件を満たす要素をフィルタリングする場合に特に便利です。ただし、コードが複雑になりすぎると可読性が低下するため、適度なシンプルさを保つことが重要です。
リストの要素を加工する例
# 1から10の数値の2乗をリストに格納
squares = [x**2 for x in range(1, 11)]
print(squares)
# 出力: [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]
条件付きのリスト内包表記
# 偶数のみをリストに格納
even_numbers = [x for x in range(1, 11) if x % 2 == 0]
print(even_numbers)
# 出力: [2, 4, 6, 8, 10]
このように、リストの内包表記は簡潔な記述と効率的なデータ操作を実現します。
ネストしたリストの内包表記
ネストしたリストの内包表記を使用することで、多次元リストを簡潔に操作できます。この技法は、リストのすべての要素に対して同じ処理を適用したり、特定の条件でフィルタリングしたりする場合に有効です。ただし、複雑な構造を扱う際には、コードが読みづらくなる可能性があるため注意が必要です。
例えば、行列のような多次元リストを平坦化したり、特定の条件に合致する要素を抽出したりする場合に便利です。
2次元リストを平坦化する例
# 2次元リストを1次元に変換
matrix = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
flattened = [num for row in matrix for num in row]
print(flattened)
# 出力: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
条件付きで要素を抽出する例
# 2次元リストから偶数のみを抽出
matrix = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
even_numbers = [num for row in matrix for num in row if num % 2 == 0]
print(even_numbers)
# 出力: [2, 4, 6, 8]
ネストしたリストの内包表記を使うと、複雑な処理もシンプルに記述できますが、適切なコメントを追加して可読性を保つことが大切です。
del 文
Pythonのdel文は、変数やリストの要素、スライスなどを削除するために使用されます。この機能を活用することで、不要なデータを効率的に削除したり、リストのサイズを調整したりすることが可能です。ただし、del文を使用すると対象のオブジェクトが即座に削除されるため、後で使用する予定がある場合は注意が必要です。
リストの特定要素を削除する場合、インデックスを指定して要素を削除します。さらに、スライスを使うことで、複数の要素を一度に削除することもできます。
特定の要素を削除する例
# リストの特定要素を削除
fruits = ["apple", "banana", "cherry", "date"]
del fruits[1]
print(fruits)
# 出力: ['apple', 'cherry', 'date']
スライスを使用して複数要素を削除する例
# リストの範囲を削除
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
del numbers[2:5]
print(numbers)
# 出力: [1, 2, 6]
また、オブジェクト全体を削除する場合にもdel文を使用します。削除された変数はその後参照できなくなるため、適切なタイミングで使用することが重要です。
オブジェクト全体を削除する例
# 変数を削除
x = 10
del x
# print(x) # NameError: name 'x' is not defined
del文は、不要なデータを効率よく管理するための便利なツールです。適切に使用することで、メモリ管理やコードの効率化に役立ちます。
Python 3 エンジニア認定基礎試験 5章 データ構造 後半

- タプルとシーケンス
- 集合型
- 辞書型 (dictionary)
- ループのテクニック
- 条件についてもう少し
- シーケンスとその他の型の比較
タプルとシーケンス
タプルはPythonにおける基本的なデータ構造の一つで、複数の値を1つのオブジェクトとしてまとめて管理するために使用されます。タプルの特徴は、リストと似た構造を持ちながらも不変(immutable)である点です。この性質により、変更不可のデータを保持したい場合や、データの整合性を保ちたい場合に利用されます。また、タプルはリストと同様にシーケンス型に分類され、インデックスやスライスを使用して要素にアクセスできます。
タプルはカンマ区切りの形式で作成され、括弧を使用して明示することもできます。タプル内には異なる型の要素を含めることが可能で、関数の複数の戻り値を扱う際にもよく利用されます。
タプルの基本的な使用例
# タプルの作成と要素へのアクセス
coordinates = (10, 20, 30)
print(coordinates[0]) # 10
print(coordinates[1:]) # (20, 30)
タプルを使った複数の戻り値の管理
# 関数から複数の値を返す
def get_person_info():
return "Alice", 25, "Engineer"
name, age, job = get_person_info()
print(name) # Alice
print(age) # 25
print(job) # Engineer
タプルは不変であるため、安全にデータを共有できる点が大きなメリットです。一方で、要素を変更できないことがデメリットとなる場合もあるため、用途に応じてリストとの使い分けを意識すると良いでしょう。
集合型
集合型(set)は、重複のないユニークな要素を保持するデータ構造です。リストやタプルと異なり、集合型では要素の順序が保証されません。この特性により、要素の重複を除外したり、効率的に集合演算(和集合、積集合、差集合など)を行ったりする場合に適しています。
集合型は、波括弧 {} または set() を使って作成します。リストやタプルを集合型に変換することも可能です。また、集合型には効率的な要素の追加・削除メソッドが備わっています。
集合の基本操作
# 集合の作成と基本操作
fruits = {"apple", "banana", "cherry"}
fruits.add("orange")
fruits.remove("banana")
print(fruits) # {'apple', 'orange', 'cherry'}
集合演算の例
# 集合演算(和集合、積集合、差集合)
set_a = {1, 2, 3}
set_b = {3, 4, 5}
union = set_a | set_b
intersection = set_a & set_b
difference = set_a - set_b
print(union) # {1, 2, 3, 4, 5}
print(intersection) # {3}
print(difference) # {1, 2}
集合型は重複を自動的に排除するため、データの整理に便利です。ただし、順序が保持されないため、要素の順番が重要な場合にはリストやタプルを使うべきです。
辞書型 (dictionary)
辞書型(dictionary)は、キーと値のペアでデータを保持するデータ構造です。キーを使って値にアクセスすることができ、リストやタプルと異なり、インデックスではなく任意のハッシュ可能なキーを使用します。辞書はデータを構造化して格納し、効率的な検索や更新が可能なため、非常に強力なツールです。
辞書は波括弧 {} を使用して作成し、コロン : でキーと値を関連付けます。また、値の追加・更新、削除、検索など、さまざまな操作が簡単に行えます。
辞書の基本操作
# 辞書の作成と要素の操作
person = {"name": "Alice", "age": 25, "job": "Engineer"}
person["age"] = 26
person["city"] = "New York"
del person["job"]
print(person) # {'name': 'Alice', 'age': 26, 'city': 'New York'}
辞書を用いた反復処理
# 辞書のキーと値を反復処理
person = {"name": "Alice", "age": 25, "job": "Engineer"}
for key, value in person.items():
print(f"{key}: {value}")
# 出力:
# name: Alice
# age: 25
# job: Engineer
辞書型は、データをキーで分類して管理したい場合に非常に便利です。一方で、キーの重複が許されないため、ユニークな識別子を意識する必要があります。適切に活用することで、効率的で見通しの良いプログラムを作成できます。
ループのテクニック
Pythonのループにはさまざまな便利なテクニックが存在し、効率的なコード記述を可能にします。特にfor文は、リストや辞書、タプルなどのシーケンス型を簡潔に操作できるため、日常的に使用されます。また、enumerateやzipなどの組み込み関数を活用することで、ループ内での複雑な処理をより簡単に実現できます。
インデックスと要素を同時に扱う
ループ内でインデックスと要素の両方が必要な場合、enumerate関数を使うと簡単に処理できます。
# リストのインデックスと要素を取得
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for index, fruit in enumerate(fruits):
print(f"インデックス: {index}, フルーツ: {fruit}")
# 出力:
# インデックス: 0, フルーツ: apple
# インデックス: 1, フルーツ: banana
# インデックス: 2, フルーツ: cherry
複数のシーケンスを同時にループ処理する
複数のリストを同時に処理する場合、zip関数を使用すると効率的です。
# 2つのリストを同時に処理
names = ["Alice", "Bob", "Charlie"]
ages = [25, 30, 35]
for name, age in zip(names, ages):
print(f"{name}は{age}歳です")
# 出力:
# Aliceは25歳です
# Bobは30歳です
# Charlieは35歳です
ループのテクニックを活用すると、冗長なコードを簡潔にし、可読性を高めることができます。ただし、複雑すぎる構造は避け、シンプルさを意識しましょう。
条件についてもう少し
条件分岐はプログラムの流れを制御するための重要な構造です。Pythonでは、if文を活用してシンプルな条件を記述できますが、複雑な条件やネストされた条件を扱う際には工夫が必要です。また、条件を簡略化するためのallやanyといった組み込み関数も便利です。
複数条件を組み合わせた例
複数の条件を組み合わせる場合、論理演算子(and、or、not)を使用すると分かりやすくなります。
# 年齢と名前の条件を組み合わせる
age = 25
name = "Alice"
if age > 20 and name.startswith("A"):
print("条件を満たしています")
else:
print("条件を満たしていません")
# 出力: 条件を満たしています
allやanyを活用した条件処理
複数の条件を簡潔に評価したい場合には、allやanyを使用することが効果的です。
# 複数条件の評価
conditions = 日付未入力
if all(conditions):
print("すべての条件を満たしています")
else:
print("いずれかの条件が満たされていません")
# 出力: すべての条件を満たしています
条件式はシンプルに保つことが大切です。複雑な条件を記述する場合は、途中で分けたり、コメントを適切に記載して可読性を確保しましょう。
シーケンスとその他の型の比較
Pythonにはリストやタプルといったシーケンス型のほかに、辞書や集合型、文字列型など多様なデータ型があります。これらの型はそれぞれ特定の用途に適しており、特徴を理解して適切に使い分けることが重要です。
リストとタプルの比較
リストとタプルの主な違いは、リストが可変であり、タプルは不変である点です。リストは要素の追加や削除が可能ですが、タプルは作成後に変更できません。
# リスト(可変)
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits.append("orange")
print(fruits) # ['apple', 'banana', 'cherry', 'orange']
# タプル(不変)
coordinates = (10, 20, 30)
# coordinates[0] = 15 # これはエラーになります
集合型とリストの比較
集合型(set)は重複を排除し、順序を保持しない点でリストと異なります。要素の順序が重要でない場合や、重複を防ぎたい場合には集合型が適しています。
# リストと集合の比較
numbers = [1, 2, 2, 3, 3]
unique_numbers = set(numbers)
print(unique_numbers) # {1, 2, 3}
print(list(unique_numbers)) # [1, 2, 3](リストに戻す)
各データ型の特徴を理解し、状況に応じて適切な型を選ぶことで、コードの効率性と可読性を高めることができます。用途に応じて型を選択し、意図が明確なコードを心がけましょう。
まとめ:Python 3 エンジニア認定基礎試験 (5章)の概要と重要ポイント
関連記事
- 独立行政法人情報処理推進機構
- Python チュートリアルドキュメント
- Python 3 エンジニア認定基礎試験
- Python 3 エンジニア認定基礎試験概要
- 初心者向けのPython3 エンジニア認定基礎試験の勉強方法まとめ
- Python 3 エンジニア認定基礎試験 (1章〜3章)合格までのロードマップ
- Python 3 エンジニア認定基礎試験 (4章)の攻略ポイント解説
- Python 3 エンジニア認定基礎試験 (5章)データ構造の完全攻略ガイド
- Python 3 エンジニア認定基礎試験(6章・7章)学習内容と対策法
- Python 3 エンジニア認定基礎試験(8章)の例外処理とエラー対策完全ガイド
- Python 3 エンジニア認定基礎試験(9章)の出題傾向と対策法
- Python 3 エンジニア認定基礎試験(10章)の頻出問題と解説
- Python 3 エンジニア認定基礎試験(11章・12章)で押さえるべき基礎事項
- Python 3 エンジニア認定基礎試験(13章〜16章)重要ポイントまとめ